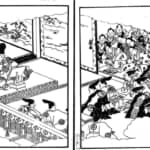父よりはるかに長く権力の座についた藤原頼通
紫式部と藤原道長をめぐる人々㊸
■摂関から院政へと変わりゆく時代の狭間に立つ
藤原頼通(よりみち)は992(正暦3)年に、藤原道長の長男として生まれた。母は左大臣を務めた源雅信の長女である源倫子(ともこ/りんし)。同じ母を持つ姉に藤原彰子(あきこ/しょうし)、弟に藤原教通(のりみち)、妹に藤原妍子、藤原威子(たけこ/いし)、藤原嬉子(よしこ/きし)がいる。
元服したのは12歳だった1003(長保5)年だが、この時に正五位下という位階を授かった。通例は従五位上とのことだから、道長の後継者として多大な期待と注目が寄せられていたことがうかがえる。
1009(寛弘6)年に権中納言、1013(長和2)年には権大納言、1015(長和4)年には左大将に就任するなど、破格の出世街道を歩んだ。
1017(寛仁元)年3月に内大臣に就任。当時、頼通は26歳。直後に父・道長より摂政の座を譲られている。当時としては史上最年少となる摂政の誕生だった。
最高権力の座についたとはいえ、父の影響力は依然として大きく、実権は道長に握られたままだった。もっとも、頼通も大臣になりたてで経験が浅く、道長に頼らざるを得ない場面は少なくなかった。事実、除目の最中に使者を派遣して道長の指示を仰いだこともあったらしい。道長は、頼通の不手際を叱責し、勘当を申し渡したこともあったほど、厳しく指導したという。
表向き、宇治で隠居する態度を明らかにしていた道長は「政務には関与せず」と言明していたようだが、周囲がそれを許さなかった。道長による実権の掌握はしばらく続いた。